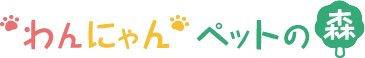猫の鳴き声にも種類があることをご存じでしょうか。鳴き声一つに猫の気持ちが表れたり、時には健康状態が分かることもあります。今回は代表的な鳴き声が表す気持ちや、猫の体調管理のために注意したい鳴き声についてご紹介します。
猫の鳴き方で気持ちがわかる
代表的な猫の鳴き声
猫の鳴き方にはさまざまなバリエーションがあります。日常生活の中で聞かれる、代表的な猫の鳴き声について見ていきましょう。
好意的な猫の鳴き声
まずは甘えてくれたり、比較的好意的な気持ちを表す鳴き声をご紹介します。次のような鳴き声が聞かれるときはコミュニケーションのチャンスかもしれません。
| 鳴き声 | 気持ち |
| ニャー(長く伸ばす)、ニャオーン、ニャオ | ご飯がほしい、遊んでほしいなどの要求 |
| ニャッ(短く鳴く)、ウニャ | 呼びかけたことへの返事 |
| グルグル、ゴロゴロ(喉を鳴らす) | 安心し、リラックスした状態。喜んでいるときに鳴きやすい。信頼してくれている証拠。 |
こんな鳴き声のはそっとしておいてあげよう
繊細な猫や、気分がよくないときは鳴き声もいつもと違うことがあります。触っているときなど嫌がって鳴くこともあるので注意しましょう。
| 鳴き声 | 気持ち |
| ニャッ(短く鳴く) | 触られるのが嫌なとき、返事をするのが面倒くさいとき |
| グルグル、ゴロゴロ(喉を鳴らす) | 病気やケガに対する不安を解消したり、回復しようとしているとき |
| ウーッ、ナー、シャーッ、フゥーッ、シューッ | 相手への威嚇、緊張や警戒しているとき。 |
| ギニャー、ミャーオ、マーオ | 痛いとき、やめてほしいときや、恐怖、パニックに陥っているとき。 |
警戒や威嚇の鳴き声を発するときは、猫がケンカ腰になっている状態なので、そっとしておいてあげることが大切です。触っているときも、短く鳴き声をあげたときは無理に構わないようにしましょう。必要以上に構うと、余計嫌がられるかもしれません。「ニャッ」は挨拶の一つでもありますが、面倒くさそうに鳴くときもあります。喉を鳴らすのも、通常は甘えてくれているときが多いのですが、状態によっては病気や不安な状況を改善しようとしている可能性があります。
特徴的な鳴き声
他にも、「カッカッ」や「ニャニャッ」、「カチカチ」などの鳴き声を出すことがあります。ちょっと変わった鳴き声ですが、獲物を狙っていたり、タイミングをつかむのにもどかしく、イライラしているときに発することが多いです。自分の方を見て、こんな鳴き声が聞こえたときは、突撃されないよう注意しましょう。
猫がかすれた鳴き声を出すときの健康状態は?
健康状態が悪いというサインかも
猫の健康は、鳴き声に表れることもあります。特に鳴き声がかすれているときは、何かしらのトラブルを抱えていることがあります。
鳴き声がかすれるときとは
元々ハスキーな鳴き声の猫はいますが、いつもよりかすれ声で鳴くときは、何かしら異常がある可能性があります。
- 声変わり
- 鳴きすぎ
- ストレス
- 病気
個体差がありますが、猫によっては人間と同じように声変わりをする場合があります。特に去勢手術を済ませたあとや、発情期のオス猫に多い傾向があります。また、性格的に寂しがり屋の猫は、飼い主のことを恋しく思って鳴きすぎから声がかれることがあります。留守にしていて、帰ってきたら枯れているようであれば「分離不安」と病気にかかっているかもしれませんので注意しましょう。ストレスや病気の場合は、他にも特徴が表れることが多いのでもう少し詳しくご紹介します。
ストレスを感じているときは大声にもなりやすい
猫がストレスを感じているときは、大声で鳴き続けることでかすれ声になることがあります。訴えるような大声で泣き止まないときは、周りにストレスがあることをアピールしていると考えられます。ただし、繊細な猫の場合は大声で鳴き続けなくとも、極度のストレスで声が出なくなる場合もあります。ストレスで声が出なくなる場合は、急にかすれ声になるというよりは、ストレスの原因が始まって1~2週間後に出やすいと言われています。
ストレスになりやすいのは、環境の変化があったときです。例えば引越しや、留守番の頻度が多くなったとき、新しい猫がきたときなどは、特に積極的にコミュニケーションを取ったり、猫がリラックスできるような状態を作ってあげましょう。他にも、トイレが汚いとストレスになることがあるので、こまめな手入れをしてあげることが大事です。
病気でかすれ声になるとき
精神的なストレスでかすれ声になるケースもあれば、体の具合が悪くてかすれることもあります。病気の場合は、全体的に食欲低下が見られます。生活環境に変わりなく、猫のストレスの原因が思い当たらない場合は次のような病気を疑ってみましょう。
- 猫風邪
- 気管虚脱
- 咽頭炎
猫風邪はウィルス感染がほとんどです。症状として鳴き声以外にくしゃみ、鼻水、発熱、角膜炎や結膜炎を併発することが多くあります。目ヤニなどは目印になりやすいので、チェックしてみてください。気管虚脱は、通常気管を丸く保っている軟骨と膜が変形し、呼吸がしづらくなることです。重度になると呼吸困難から命に関わる危険性もあるので、なるべく早い処置が必要です。咽頭炎はのどの炎症ですが、猫の場合よだれが増える傾向があります。ひどくなると声が出なくなることもあります。
猫が大きな声で鳴くときとは?
発情期と病気のときとの違い
猫が大きな声で鳴くときは、病気や不安を感じているとき以外に、発情期というケースもあります。発情期の場合の鳴き声の特徴を知っておいて、見分けられるようにしておきましょう。
発情期の鳴き方はいつもよりだみ声
大きな声で鳴く場合でも、「アォーン!」「ウオォ~ン!」など、いつもと違うダミ声で鳴く場合は発情期の可能性があります。「ンニャーオ!」と相手に自分をアピールして求愛していると考えられます。発情期は避妊、去勢手術をした猫の場合比較的マシになりますが、メス、オスに限らず大きな声で鳴き続けるのが特徴です。時には一晩中鳴くこともあります。
排便時に苦しそうに鳴く場合は便秘かも
便秘のときも、苦しそうに鳴くことがあります。普段と違い、大きな声で鳴くこともあります。猫がトイレに行っているとき変な声で苦しそうになくようであれば、疑ってみてください。
大きな声で鳴いているときは、鳴き声以外の様子もチェック
病気かもしれない、という判断は、猫の鳴き声以外の様子をチェックすることも重要です。前述した猫風邪に見られる目ヤニや咽頭炎によるよだれもそうですが、食欲はあるか、水は飲んでいるかなども確認しましょう。便秘のように、どこで鳴いているか、変な動きをしていないかと全体的な様子をチェックすることで異常を感じられることもできます。変だなと感じたときは獣医に相談しましょう。
猫なりに鳴き声で感情や健康の変化を知らせてくれている
いつもと違う鳴き声をするときは周囲の環境や猫の様子をじっくり確認
猫とは言葉で会話はできませんが、鳴き声から気持ちを察したり、体調の異変に気づくことはできます。特にかすれ声のときや、苦しそうだったり、大きな声で鳴く場合は、ストレスや病気など健康に問題があることが多くあります。ストレスはすぐに表れないことがありますが、繊細な性格の猫や、環境の変化があったときは注意して見守ってあげてください。できるだけ猫がリラックスできる状態を作ってあげることが必要です。
特に周囲の環境に変化がないときは、体調が悪いのかもしれません。病気の場合は、食欲がなかったり、鼻水や熱、目やになど、体に症状が出ていることが多いので、全体をチェックするようにしましょう。同じ鳴き声でも、大人しくしてご機嫌に見えて、実は嫌がっているのを鳴き声で表していたり、病気の不安を紛らわせていることもあるので、都度猫の様子をチェックしながらコミュニケーションを取るといいかもしれません。
猫の鳴き声で分かる気持ちと健康のチェック方法
- 猫の鳴き声は、甘えていたりご機嫌だったり、鳴き方で猫の気持ちが表れる。
- 触っているときに「ニャッ」と短く鳴かれたら嫌がっている証拠。触り続けると威嚇されたり、嫌がられたりしやすいのでほどほどに。
- ご機嫌な証拠といわれるノドを鳴らす行動も、体調不良時や不安なときに起こすことも多いので注意。
- かすれ声やいつもより大きな声で鳴くときは、ストレスや病気の可能性大。環境や猫の様子に変化がないか十分チェックしよう。トイレで鳴いているときは便秘かも。